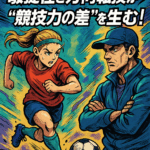【女子サッカー指導者必見】敏捷性と方向転換が“競技力の差”を生む理由とは?
「走れる子=強い子」ではない?
これまで多くの指導者が「足の速さ」や「筋力」に注目してきた中で、最新の研究が示したのは意外な結果でした。
試合で活躍する女子選手ほど、“方向転換の速さ”や“瞬時の反応”に優れていたのです。
🔍 研究のポイント:高校女子サッカー部での比較
- 対象:高校女子サッカーチームの1軍13名・2軍15名(計28名)
- 実施したテスト:
- リアクティブシャトルテスト(視覚刺激に反応し180°方向転換を繰り返す)
- プロアジリティテスト(あらかじめ方向が決まっている180°方向転換)
- 10mスプリント、カウンタームーブメントジャンプ(CMJ)、立ち幅跳びなど
✅ 明らかになったこと
- 1軍の選手はリアクティブシャトルテストとプロアジリティテストの記録が有意に優れていた
- リアクティブシャトルテストは筋力やジャンプ力とは相関が低く、**“認知・判断・動作の連携”**が重要
- 一方、プロアジリティテストは直線スピードや跳躍力と相関が高く、筋力などのフィジカルの影響も受けやすい
🧠 指導者が注目すべき“反応型アジリティ”
リアクティブシャトルテストは、ただ動くだけではなく、外部刺激(光)に素早く反応し動き出す能力を測定します。
これは、試合中に起きる「目の前のパスに反応して動き出す」「相手の動きを見て逆を取る」など、実戦に直結する動作そのもの。
つまり、アジリティ=単なる俊敏さではなく、“見る→判断する→即座に動く”までの一連のスキルであると分かります。
🎯 現場での取り組み提案
✅ 1. 判断を伴うアジリティドリルの導入
- 色・音・合図によるスタート反応トレーニング
- 「どちらに動くか分からない状況」での方向転換ドリル
- パス or シュートの判断付きスプリント練習
提案:「反射神経」ではなく、「反応判断能力」を育てる設計を。
✅ 2. COD(Change of Direction)とアジリティは分けて考える
- CODは「決められた方向へ素早く切り返す能力」=物理的な動作スピード
- アジリティは「予測しづらい状況で反応し動く能力」=認知&反応+動作
提案:両方をバランスよく鍛える練習を設計する
(例:「決まった動き」と「ランダムな動き」のセットメニュー)
✅ 3. 試合期には“リアクティブ系”を軽めに継続
- 疲労がある中でも、認知・判断の質を落とさず動けるかをキープするための軽負荷アジリティドリルをルーティンに
⚠️ 注意すべき点
- ジャンプ力や筋力が高くても、リアクティブアジリティが高いとは限らない
- 視覚刺激が加わると、一瞬の判断と動作選択ミスが起きやすくなる
- だからこそ、繰り返しトレーニングして“瞬間判断に強い身体”をつくる必要がある
✨ まとめ|「見て→判断して→動く」選手が試合を制する!
この研究は、「身体の強さ」だけでは女子選手の競技力を語れないことを教えてくれます。
指導現場では、反応型アジリティや認知トレーニングの導入がますます重要になるでしょう。
📌 論文情報
- 論文タイトル:ユース女子サッカー選手における敏捷性、方向転換能力、競技レベルの関係
- 著者:伊藤宏長・内藤雄斗(早稲田大学/パフォーマンスアップチーム リザルト)
- 掲載誌:Football Science Vol.22, 2025年
- 掲載URL:https://www.shobix.co.jp/jssf/index.cfm?page=3
🧪 あなたのチームで“実際に”測ってみませんか?
この記事で紹介したようなアジリティや方向転換能力の違いが、実際にチームの中でどう表れるのか――
それを客観的に知る手段のひとつが「フィジカルテスト」です。
🎁 現在、初回無料キャンペーン実施中!
- ✅ 成長スパート(PHV)の予測
- ✅ 敏捷性・ジャンプ力・スプリント力の測定
- ✅ 測定結果に応じた個別トレーニング・栄養アドバイスつき
「うちのチームにも導入してみたい」
「まずは詳しく話を聞いてみたい」
という方は、下記のフォームからお気軽にご連絡ください👇
SNSでフォローする